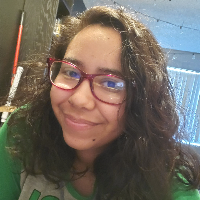映画「フリーガイ」の哲学:現実、目的、そして変化について

ほとんどのシミュレーション映画は、私たちがテクノロジーの進歩から得たお気に入りのアイデアとして、ビデオゲームを舞台にしています。ただし、Ready Player One のようなビデオゲームには人間が関わっています。日本の番組「ソードアート・オンライン」でさえ、ビデオゲームでの生活に焦点を当てています。
しかし、フリーガイでは、ガイはNPCとしてビデオゲームに所属しています。このアイデアはゲームのジャンルでは新しいものですが、トゥルーマンショーでは新しいものではありません。映画を見たことがない方のために説明すると、「トルーマンショー」は、トルーマンという男が、テレビの生放送に出ていることとのつながりを作ることで、自分の世界が人工的なものであることを発見するというものです。
映画の最後で、トルーマンはショーから逃れて現実に入ります。ガイはNPCとして人工的にフリーシティというゲームに所属しているため、これはガイにはない選択肢です。言い換えれば、映画はシミュレーション理論そのもので遊んできたように、フリーガイは代わりに偽物になるという考えで遊んできたのです。
ただし、現実またはシミュレーション理論、別名マトリックスについての質問は、17世紀にフランスの哲学者ルネ・デカルトによって最初に尋ねられました。このアイデアは、情報を処理する感覚の信頼性が低いことから生まれたもので、彼は現実と知識に対する認識に疑問を抱かせました。
同時に、この質問から彼の有名なフレーズ「cogito ergo sum」が浮かび上がりました。デカルトが疑うことができなかったのは、彼の存在だけだったからです。なぜなら、デカルトが疑うことができなかったのは、フリーガイの目的の問題に集中し、結びついているアイデアだからです。
ガイはNPCだ、だから何?
ガイは自分がNPCであることを知らないし、自分で発見することもない。ゲーマーのミリーは、自分が偽物だとガイに言わなければならず、彼の世界は崩壊しました。
しかし、ガイが仮説として親友のところに行くと、「じゃあ、私が偽物だったらどうする?」と言って見通しを立てます。彼は続けて、ガイと過ごしている瞬間が現実であることを知っているので、それは問題ではないと言います。
この発言だけで、ガイの現実に対する見方は、不安を誘発するものから無関心へと変わります。なぜなら、彼の存在が現実のものであれば、心配する必要はないはずだからです。しかし、現実の問題は人々に大きな負担をかける可能性があるため、このメッセージは聴衆にも送られます。

男は生きることで目的を育む.
しかし、ガイは自分がNPCであることを知る前に、自分の人生に行き詰まっていると感じていました。彼は素晴らしい街に住んでいたので幸せでしたが、それはありふれたことであり、もっと多くのことを望んでいました。
これは彼が生き返ったときの不具合のように思えるかもしれませんが、彼は夢の少女に出会うまでこのように感じるようにプログラムされていました。これはミリーだったので、ミリーに出会うと、彼はゲーマーのように生きることで自分の人生を管理し始め、それが彼が感性を獲得し始めた頃の真の目印となります。
そして、NPCは作成したプログラムに従うだけなので、ガイがコードから一歩踏み出すと、現実の生活とは、私たちが人生で本当にやりたいことをしていることであることがわかります。
メディアは、誰かの人生にいかに幸せと目的があるかを伝えています。その多くは、教育を受け、結婚し、子供をもうけるという、誰もが望んでいなければ生きなければならない人生ではないのに、教育を受け、結婚し、子供をもうけるという、これらの奇妙なマイルストーンに関係しています。
つまり、生きることとは、自分がどう生きたいかということであり、社会がどう生きるべきかということではありません。ガイは、従いたいと願っていたゲーマーのように生きることでこれを実現しています。しかし、ゲーマーの役割は彼の社会に存在するライフスタイルなので、それを彼が望み、得ているものであることを示すことは、たとえ誰かが本当に望んでいるのが母親や妻のように社会で受け入れられているライフスタイルであったとしても、それが羊にはならないということです。

フリーガイは個人ができる変化を見せてくれます.
ガイはゲーマーのような生活を送り始めましたが、ゲーマーの生活は本物のゲーマーの特徴であるサングラスをかけている人々だけがゲーマーであり、サングラスをかけていない人をNPCにするというものでした。
とはいえ、メガネをかけた人々、ゲーマーは、NPCがプログラムされた生活を送ることを余儀なくされている間、やりたいことを何でもしてフリーシティをコントロールしています。これは、政府や裕福な人々がやりたいことを何でもして社会を支配しているのに、一般市民は自分たちが作り上げたシステムから制限されているという現実の生活と似ているように思えます。
しかし、ガイは他のNPCと交流することで彼らの感性を生み出し、新しいことをするようになります。これは、ガイがミリーを見た後に生き返るように人工的にコード化され、交流したNPCの間で連鎖反応を引き起こしたためです。つまり、ガイは生きているようにコード化されていたとしても、ガイは個人の小さな行為がどのように変化をもたらすかを示しているのです。

ガイはまた、排除中にNPCを集めてストライキを行います。これは、ストライキが国際的な注目を集めたため、複数の人が抗議に参加した場合に生じる変化を示しています。
ガイはゲーム内で盗まれた知的財産を暴露したかもしれませんが、NPCのストライキがなければ、それに注目することはできなかったでしょう。これは、NPCがゲーマーが遊ぶためのコード化されたプログラム以上のものであることを示しています。翻訳すると、このテーマは、公民権が政府の利益のためにいじられたり悪用されたりする一方で、市民が公民権のためにどのように戦うかに焦点を当てています。
映画では、これは企業の世界が2人のゲーム開発者、ミリーとキーズの知的財産を自分たちのものとして名乗って盗むことと並行して起こっています。キーズはフリーシティのプログラマー兼デベロッパーとして知られず、結局同社の不具合修正者になってしまったため、このことが彼らの生活にも影響を及ぼしました。そして、政府が市民の生活をどのように統制し、制限しているかが明らかになったのは、彼の台無しにされた夢を通してです。
しかし、ミリーは会社に対して訴訟を起こし、ゲーム内の証拠を探すことで権利を争います。幸運なことに、ガイが証拠を発見したライブストリームを通じて、ミリーは訴訟に勝つことができました。これは、市民が自分たちの権利に対して持っている強さを示しています。
フリーガイは楽しい映画として楽しむことを意図していますが、観客が思い通りに生きることを奨励しています。なぜなら、現実とは関係なく、シミュレーション中であろうとなかろうと、私たちの経験は現実のものであり、私たちは思い通りに生きることによってそれを最大限に生かすべきだからです。
誰もその答えを見つけることができないため、目的のメッセージは明確ではありませんが、皮肉なことに、生きることでその質問に答えられます。私たちは生きることの目的を決して知ることはできませんが、私たちはできる限り最高の人生を送るべきであり、それが究極的には私たちの目的になり得ます。
そして、生活には抑圧的なシステムからの障壁が伴うため、個人や人々のグループにインスピレーションを与える大小さまざまな行為によって変化を生み出すことができます。いずれにせよ、変化を求める交流と運動は、他の人々が自分のやりたいことを行い、より良い生活を送る能力と権利を持つための余地を広げるものです。
Opinions and Perspectives
私が魅力的だと思ったのは、ガイが自分が偽物であることを受け入れたことが、彼を解放したことだ。時には、私たちが何であるかよりも、私たちが誰であるかを受け入れることが重要だ。
NPCと現実社会の支配との類似点は非常に巧妙だ。単なるビデオゲームのキャラクターの話ではなく、私たちを制限するシステムから解放されることについてだ。
『フリー・ガイ』が、あんなに楽しい方法で実存的なテーマを探求しているのが大好きだ。NPCが自己認識を持つというアイデアは、意識や自由意志について深く考えさせられる